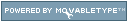◆アリストテレス(三浦洋訳)『政治学(上・下)』光文社、2023年
本文だけで上下合わせて900ページ、そこに親切な解説がついて読み通すのに結構時間がかかりましたが、せっかくなので上巻4時間半、下巻3時間半くらいかけてページをめくり直し、メモを作りました。弊管理人の目にとまったところだけ抜き出し、しかも異常なスピードで駆け抜けたため、正確性・妥当性には全く自信がありません。遙か下のほうに、後から「あれどこに書いてあったっけな」というのが分かる原メモみたいなものを付けて、とりあえず現時点でのざっくり理解と、思ったことを書き付けておきます。
著者はとにかく何でも分析ニキで、自然・人間・社会への関心の広さと観察眼は卓越しています。そして今の西側思想世界は、ニキが考えたことの深化や、それへの批判でできてるんだなと改めて思いました。
【第1巻】
国家は人が生きるために発生し、「善く生きる」ために存在している。家(男女、奴隷関係)→家が集まって村→村が集まって国家が発生する、という「自然過程」が説明される。とにかく社会関係も自然なものだと考えられ「自然は人間のためにある」とか「身体を使うことが最善であるような人は自然本性的に奴隷」「妻子は夫に支配されるべきもの」など現在の感覚からするとおいおいと思うことも多く、また極めて現状肯定的・運命論的だ。ニキの体系をどこまでつまみ食いしていいものかと悩むところではある。
一方で、分析対象を構成要素にまで分解して成り立ちを考える手つきは、デカルト以降の科学にも通じるところかなと思った。交換から貨幣が生まれ、そして自然でない利殖術・財テクの発生まで行ってしまうところからはマルクスと、ついでにカイヨワを思い起こしてしまった。
エピソードとしては「自然哲学者も本気になれば科学を使って金儲けができるが、そんなもん真剣にやるようなことではないのでやってないだけだ」ということを示すタレスの事例が面白かった。まあ国には金儲けの才覚を持った人も必要なんだけどな。
【第2巻】
先行研究のレビュー。主にはソクラテス、プラトン批判が続く。国家における「妻子の共有」や国家が一つになること、私有財産の否定といったものに対する反論。ここは個人的にあまり引っかからなかったが、多様性を認めたり(ただし女性を自由にするような国制を「有害」と言っており、現在の意味の「多様性」ではない。単にいろんな人がいる、くらいの意味)、善く生きるには先立つものが必要だ、という現実主義なところは面白いなと思った。カネがなければ「気前のよさ」という自由人の徳を発揮することができないんだよね。
そのあとには、別の人たちの国制論や、クレタ、ラケダイモン(=スパルタ)、カルタゴ、ソロンの国政運営の検討が続く。このあたりはさらっと。
【第3巻】
ここから有名な国制の分類に入る。
準備運動として、まず国を構成する「市民とは何か」を規定する。それは国の運営に関わる人たち、ということである(しかしそこには手を使って働く職人も子どもも含まれない)。国は生きるための相互扶助の場であるとともに、人のために善く生きること、「公共善」の追求の場であるとされる。サンデルがよく使う「公共善」がここで出てきた。
そして、最高権限を占めているのが1人か、少数か、多数か。また支配者のための悪い統治か、みんなのための正しい統治か、で6種類の国制が紹介される。
<正しい国制>
・支配者が1人:王制(世襲制/選出制)。支配の劣化が起きやすいのが難点
・支配者が少数者:貴族制(最善の人々アリストイ/最善の目的アリストンに由来)。これが最善の国制
・支配者が多数者:共和制(ポリーテイアー。戦士が最高権限を持つ。戦争の徳であれば多数者が極められるから)
<逸脱した国制>市民に共通の利益を目指していない国制
・支配者が1人:独裁制(単独者のための国制)
・支配者が少数者:寡頭制(富裕者のための国制)
・支配者が多数者:民主制(貧困者のための国制)。少数者のものを取り上げ、多数者に分配しようとする。多数者主権+個人の自由を特徴とする
なぜ支配者のための統治が悪のか。それは、市民と市民の間の関係が「主人と奴隷」のようになってしまい「自由な市民の共同体」という本来のあり方から逸脱するからだ。この、奴隷も女性も子どももいない「戦う男」だけの上澄みワールドだけ見ればの話しではあるが、今の「民主主義」の理念に近くなる。
あっと思ったのは、「悪い国制」の中で、少数者が支配する「寡頭制」と多数者が支配する「民主制」の違いに関する指摘だ。両者の違いは本質的には支配者の多寡ではなく「金持ちによる支配か、貧乏人による支配か」だという。バーニー・サンダースが「Oligarchyと闘う」と言っていたのは「金持ち支配じゃあかんやろ」という、古典を正しく踏まえたキャッチフレーズだったんだなあと。
そして、「対等な人を対等に扱う」という、単純な平等論とも格差肯定とも違う正義のあり方は、ロールズやノージックで再燃した「分配的正義」の源流だった。
あと、「傑出した個人」をどう扱うかがちょっとした難問として取り上げられているのも面白かった。自由で対等な市民同士の支配関係にとって、突出した人の存在はそぐわないので、陶片追放などで放逐されてしまうのが常だ。しかし、そういう人は最高指導者(王)になってしまうという手もあるのではないか。
【第4巻】
ここでは、とりあえず理想の国制は置いておいて、「現実的な最善の国制」という実用的な課題を考える。現実に多い国制は民主制と寡頭制なので、そのあたりが中心になる。やっていることの大半はおのおのの国制の細かな分析で、そこはまああまり深入りしない。
それぞれの国制をどう捉えるかは、解説(上巻p.596)のまとめが分かりやすい。
・貧困者が自由を尊重するのが「民主制」
・富裕者が富を尊重するのが「寡頭制」
・上記二つを混合したのが「共和制」(ラケダイモン人の国制が例。貧困者、富裕者の子どもがそれぞれ教育を受けられる点で民主制的、公職者がくじ引きではなく選出制な点で寡頭制的)
・そこに徳の尊重が加わると「貴族制」(いろんな人が「この国は自分にとって恩恵がある」と思えることで善い国制になる)
最善の国制はと言われれば貴族制である。が、現実はいろんな国にいろんな事情があるので、各国が置かれた状況の中で一番安定するものを選べばいいよ、というのも現実主義の考え方。
「中間層が厚いことが民主制の安定の要だ」という指摘には「へえ」と思った。中庸を好む立場からは当然といえば当然だが、中間層は陰謀の対象にも嫉妬の対象にもなりにくいという指摘は鋭い。また中間層は、寡頭制に傾きそうになったら貧困層に加勢して揺り戻し、極端な民主制=貧困者支配に向かいそうになったら富裕層に加勢して引き戻す「バランサー」となり、最悪の国制である独裁制の出現を防止するという役割を見いだしているのは面白い。
14章では、ものごとを決めるときに市民全員で決める(民主制的な決め方)か、あるいは一部の人に判断を委ねるか(寡頭制的な決め方)、この二つのブレンドによって生まれてくるいろんな「決め方のバリエーション」が扱われていた。今の民主主義と自由主義―多数者の決定と、専門知による決定―のバランス問題の胚胎だろうか。
【第5巻】
「現実的な最善国家」の話の続きで、「国家はどういうときに揺らぐのか、安定させるにはどうしたらいいか」というトピックが展開される。
ざくっと言うと、社会が不安定化する根本要因は、「対等な人を対等に扱う」という分配の鉄則を守らない、つまり利益や名誉を適切に分配しない時だ。
国制を安定させる方策は簡単で、上に述べた不安定化要因と逆のことをすればよい。
民主制の場合に必要なのは、「金持ちから取って貧乏人に配れ」という民衆指導者が出現し、貧困層と富裕層の対立が深まって国を不安定化するのを避けること。ある一人の突出した存在をつくらないこと。「富裕者から取って貧困者に配る」という対立的な方法ではなく、報酬つき公職を適切に分配することを通じて財産を平準化させること。汚職をしないこと。
なお、民主制をなぜ「悪い国制」のほうに分類するかについて、「民主制は多数者支配+個人の自由。だが自由奔放であることは欲望への隷属となるので低劣な生き方である」と説明しているのが面白かった。そうね、自由は節制という徳と衝突するね。
いろんな国制について上記のような分析と提言をしているが、独裁制についても「なぜ独裁制が揺らぐのか」「揺らがないためにどうすればいいか」という「独裁者に役立つ悪のマニュアル」を提示してしまっているのも興味深かった。
独裁制を安定化させる方策として(1)独裁を強める方向と(2)正しい国制である王制に近づける方向、の二つが提示されている。
(1:独裁を強める方向)では市民が集まる機会を減らし、監視状態に置き、密告を奨励する。階層を分断する。被支配者を貧困状態に置くことが具体策だ。つまり「被支配者が小さなことばかり意識するように仕向ける」「被支配者が互いに信頼しないようにする」「被支配者の行動力を殺ぐ」ということ。こわい。
(2:王制に近づける方向)は、公金について潔白でいること、畏敬の念を抱かせるよう威厳を持つこと、享楽を慎むこと、優れた人に名誉を与えることが具体策になる。
【第6巻】
民主制と寡頭制の特徴と、国を息長く存続させるための政策を深掘りする。
民主制の要は「自由」であり、自由は(1)分配が個々人の価値ではなく人の数に基づく(2)個人が望むように生きること、という二つの側面を持つ。
一般的には貧乏人が多数なので(1)の帰結として民主制は貧乏人による支配となり、卑しさ、貧困、低俗が特徴となる。これは寡頭制の逆となる。
また(2)からは「できるだけ他人に支配されたくない」ことに基づいた制度が帰結する。公職(≒行政)は全員参加のくじ引きで任期は短期間、再任は限定される形になる。裁判(司法)では全員が裁判員になる。民会(≒立法)が最高の権限を持ち、多数者の意見が正義とみなされる。まあ力づくで決めるよりはマシである(暴力で勝てる人は真理を顧みないから)。
上記のような分析を読んでううむと思いながら次の第7巻に進んでみたら「人々の同質性が高い社会では交代制で支配することが適切になる」という記述があった(下巻p.237)。国民に極端な所得格差がなく、身分や男女の差別が制度的に廃止され、一定水準の教育が行き渡ったような社会であれば、民主制は「正しい国制」となるのかもしれないな。
寡頭制は、公職に就く人の財産要件をうまく調整することでいい制度になる。重要な公職(上位職)には高いハードル、必要不可欠な公職(現場職)に低いハードルを課し、かつ公職参入者が非参入者よりちょっと多くなるくらいにすると安定するということだろう。なお門閥制は独裁に近い最悪の寡頭制とされている。
【第7巻】
ここからは、理想的な最善の国制に関する考察。
まず個人の「最善の生」あるいは「至福」って何だ、というところから話が始まる。「魂の善(徳)」である勇気、節制、正義、思慮が必要で、これによって「外的な善」である富、財貨、権力、名誉が獲得される。他に「身体の善」つまり健康も必要となる。
個人の善は国家の善につながるが、では個人としては政治に関与すべきか、それとも支配したりされたりする世界とは距離を取って哲学するべきか、という問いが次に出てくる。
著者の考えでは、「幸福」すなわち「善い実践」なので、政治をやるのが必ずしも低級なことだとは言えない。ただし観想とか思考はもっと直接的に幸福の実践となるので、哲学して生きることも大切だといえる。ちょっと分かりにくいが、解説(下巻p.422)によると、二つの生き方は相互排他的ではないということらしい。
次に、理想的な国はどんな構成か、に関する話が始まっていく。
キーワードは「自足」で、人口規模は国家がさまざまな機能を具えて自足できるために大きいほうがいいが、秩序が保てる程度が上限になる。言い換えると、だいたい国民がどんな人で構成されているかが把握できる程度。国土も同様に、国全体が想像できる程度の大きさがいい。
国の構成要素は食料/道具製作の技術/武器/財貨/祭祀/国家運営機構で、これらを市民で分担する。若い人は体力があるから戦士となり、老人は思慮があるから審議員や祭司をやるなど、年齢で役割を振られることになる。結局は全市民がライフステージに応じていろんな役割を担いながら国家運営に参画していく。全員参加なので、一人一人が優れていることが望ましい。国と個人がともに目指すところは「平和」と「閑暇」である。「知への愛、節制、正義」をもって、得られた平和と閑暇をうまく消費するのだ。
市民の条件は、まず自然本性として「知性と情」があることが必要(で、ギリシャ人はそれを具えていると自画自賛)。他に「習慣」と「理性」が必要とされ、これらは教育を通じて涵養される。【第8章】にかけて子作りの適齢期(女性18歳、男性37歳ごろだそう)、体力作り、子どもができたら何を食べさせるか、教育は何を教えるか、など、とにかくいろんなことを考えていく。スポーツと音楽は特に検討されるが、いずれも市民として必要ではあるが、やり過ぎてアスリートとかミュージシャンになることは推奨されない。いいところでやめて国家運営の教育に入ろうなということだろう。
続きを読む "政治学" »